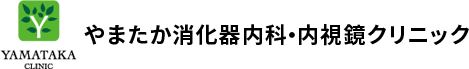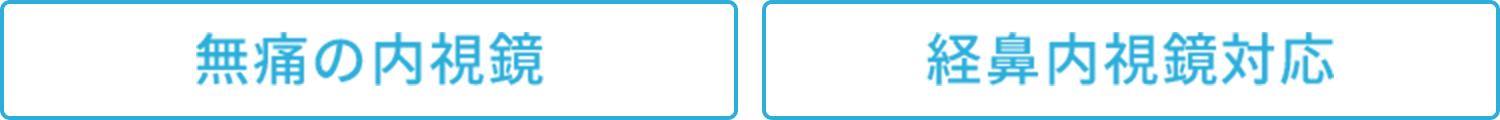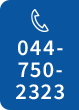潰瘍性大腸炎とは
 潰瘍性大腸炎は炎症性腸疾患の一種で、大腸粘膜を中心に慢性的な炎症が発生し、びらんや潰瘍が形成される疾患です。腹痛や下痢、血便などが主な症状となります。これらの症状が起こる活動期(再燃期)と症状が治まる寛解期を繰り返すことが特徴で、寛解期に症状が治まったからと自己判断で治療を止めてしまうと再燃期に移行するため注意しましょう。
潰瘍性大腸炎は炎症性腸疾患の一種で、大腸粘膜を中心に慢性的な炎症が発生し、びらんや潰瘍が形成される疾患です。腹痛や下痢、血便などが主な症状となります。これらの症状が起こる活動期(再燃期)と症状が治まる寛解期を繰り返すことが特徴で、寛解期に症状が治まったからと自己判断で治療を止めてしまうと再燃期に移行するため注意しましょう。
潰瘍性大腸炎は炎症範囲により、直腸炎型、左側大腸炎型、全大腸炎型、右側大腸炎型、区域性大腸炎型に分類されます。炎症部位や程度に応じて症状に違いがあります。
若年層の発症が目立ちますが、様々な年代層で発症する可能性があり、全体としては発症数が増えてきています。
現在のところ原因が明確になっておらず、完治させる治療法が確立されていないため、厚生労働省より難病に指定されています。そのため、治療目標は寛解期への移行・維持となります。
潰瘍性大腸炎の原因
潰瘍性大腸炎の原因ははっきりとしていませんが、要因は様々なものが考えられます。遺伝的要因もあると言われており、発症に関わる免疫系の遺伝子もいくつか発見されています。その他、食生活も影響しているのではないかと言われています。
潰瘍性大腸炎の症状
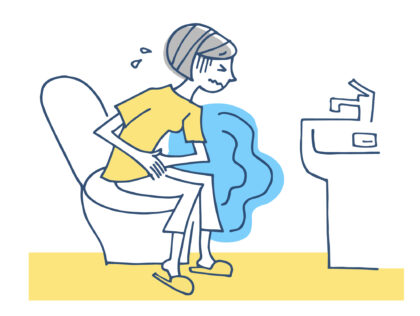 主な症状には、下痢、粘液便、血便が挙げられます。また、腹痛や排便回数の増加、残便感などの症状もよく現れます。
主な症状には、下痢、粘液便、血便が挙げられます。また、腹痛や排便回数の増加、残便感などの症状もよく現れます。
病状が進行して炎症範囲が拡大すると栄養の吸収が障害され、栄養失調や体重減少が発生することもあります。また、病変部から出血による貧血、発熱、腸管の狭窄・閉塞なども発生することがあります。潰瘍性大腸炎の炎症を放置していると、大腸がんにも繋がる恐れがあります。
潰瘍性大腸炎の検査・診断
 腹痛や下痢、粘液便、血便などの症状は薬剤性腸炎や感染症でも起こります。そのため、適切な治療を行うためにも鑑別診断が欠かせません。
腹痛や下痢、粘液便、血便などの症状は薬剤性腸炎や感染症でも起こります。そのため、適切な治療を行うためにも鑑別診断が欠かせません。
まずは問診にて服用薬や家族歴、海外渡航歴などを詳しくお聞きし、感染症の可能性がある場合は細菌学的検査や寄生虫学的検査などを実施します。薬剤性腸炎や感染症ではないと判明した場合、大腸カメラ検査により大腸全域の粘膜を観察し、病変の有無や状態を確認します。怪しい病変が見つかった場合、組織を採取して病理検査に回すことで、確定診断が可能です。
大腸カメラ検査では潰瘍性大腸炎特有の病変(潰瘍や血管透過性低下など)を確認できます。同様の症状を示すクローン病は別の特有の疾患があるため、正確に鑑別することが大切です。
潰瘍性大腸炎の治療
完治させる治療法が確立されていないため、治療は炎症を鎮めて寛解期に導入し、その状態をなるべく長く保つことが目標となります。
再燃期に移行しないためにも寛解期でも治療を続ける必要があり、活動期(再燃期)は炎症発生部位や範囲、程度により治療法が異なります。炎症を鎮める薬物療法が中心となり、5‐アミノサリチル酸製剤(5‐ASA製剤)、重症例では短期間のみステロイドを使います。これらの薬剤でも症状が改善しない場合は、血球成分除去療法や免疫調節薬、生物学的製剤の投与が行われます。
寛解期を維持できれば、発症前と遜色ない生活を送ることが可能です。なお、増悪した場合は外科手術を選択することもあります。
文責:山高クリニック 院長 山高 浩一