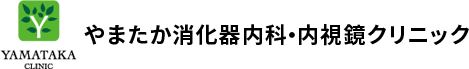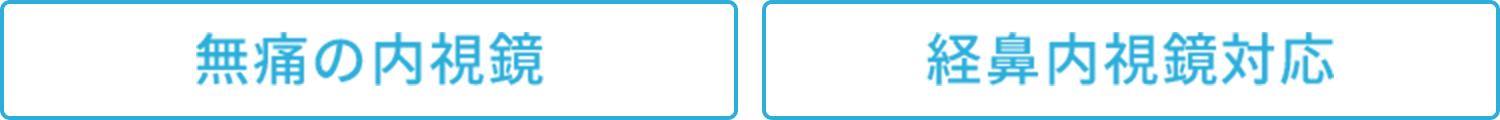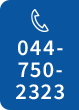逆流性食道炎とは
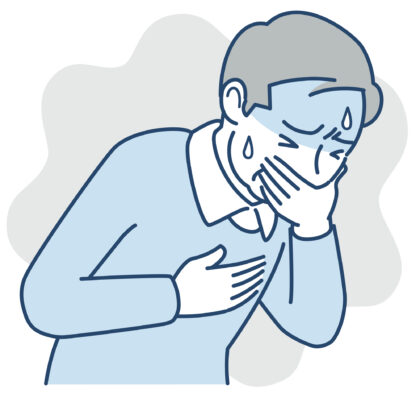 逆流性食道炎は、強酸の胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜に炎症が発生する疾患です。加齢に伴って筋肉や蠕動運動が弱まることで発症リスクが高まります。なお、若い方でも腹部への強い圧迫や生活習慣の乱れなどにより発症するケースも増えており、食事の欧米化も影響していると考えられています。
逆流性食道炎は、強酸の胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜に炎症が発生する疾患です。加齢に伴って筋肉や蠕動運動が弱まることで発症リスクが高まります。なお、若い方でも腹部への強い圧迫や生活習慣の乱れなどにより発症するケースも増えており、食事の欧米化も影響していると考えられています。
また、逆流性食道炎が原因となる「バレット食道」も増えていると言われています。これは、食道粘膜を覆う扁平上皮が円柱上皮に置き換わる状態です。
逆流性食道炎とバレット食道は、食道胃接合部がんを引き起こすリスクがあるため、定期健診の受診が重要です。食道粘膜の炎症は薬物療法によって改善できますが、放置して炎症が長期間に及ぶと食道がんのリスクが高まります。こうした深刻な状態を回避するには、生活習慣の改善とともに、専門の医療機関で炎症を鎮めるための治療を受けることが必要です。
よくある症状
- のどの違和感
- のどのつかえ感
- 飲み込みにくさ
- のどの痛み
- 咳
- 声がれ
- 胸やけ
- 胸痛
- 胃もたれ
- げっぷ
- 呑酸(酸っぱいげっぷ)
など
逆流が発生する原因
逆流の原因は多岐にわたり、以下が主な要因となります。
原因は胃カメラ検査によって特定可能で、適切な治療を行うことで再発を防止できます。
食道裂孔の弛緩
胸部と腹部を隔てる横隔膜は内臓を支える役目を担っており、呼吸にとって欠かせない筋肉です。胸部の食道は横隔膜にある食道裂孔という穴を通り胃に繋がっています。食べ物はこの通路を通り胃へと運ばれます。食道裂孔が緩んだ場合、胃酸の逆流が発生します。また、胃の一部が胸腔内に飛び出す食道裂孔ヘルニアが発生している場合も逆流リスクが高まります。
食道裂孔は加齢に伴って弛緩していくため注意が必要です。
下部食道括約筋の弛緩
食道と胃の境目には下部食道括約筋という筋肉が存在しています。食事以外では胃の内容物が逆流しないように、下部食道括約筋は閉じています。しかし、加齢に伴って衰えていくことで、逆流リスクが高まります。
蠕動運動の低下
消化管は拡張・収縮という蠕動運動を繰り返すことで内容物を次の臓器に送ります。
この蠕動運動が低下すると、逆流が起こりやすくなり、逆流したものを戻す力も弱まります。結果として、食道粘膜が胃液に長時間晒されると炎症が発生します。
腹圧の上昇
猫背などの姿勢の乱れ、ベルトやコルセットなどによる締め付け、肥満や妊娠、腹部に力を入れる力仕事などにより腹圧が上昇すると、逆流リスクが高まります。
内服薬の副作用
高血圧や喘息、心臓病などで用いるお薬は副作用として食道の筋肉が緩むことがあります。逆流性食道炎の原因としてお薬の副作用が疑われる場合、処方内容を変更することで症状が解消することがあります。副作用の原因となるお薬を中断できない場合、炎症を鎮めるための逆流性食道炎のお薬も併せて使用する必要があります。常用しているお薬がある場合は、受診時にお薬手帳あるいはお薬自体をお持ちください。
また、ピロリ菌の除菌治療中の場合、胃粘膜の機能が回復する過程で胃酸の分泌が多くなり、逆流性食道炎の症状が起こることがあります。これは胃粘膜の機能が回復してきているサインですので安心してください。
検査
 逆流性食道炎の検査では胃カメラ検査を行います。胃カメラ検査は食道を含む上部消化管粘膜を直接観察できる検査で、炎症などの病変を発見できます。怪しい病変が見つかった場合、組織を採取して病理検査に回すことで確定診断に繋げられます。また、逆流性食道炎に併発する可能性が高い食道裂孔ヘルニアも調べられます。
逆流性食道炎の検査では胃カメラ検査を行います。胃カメラ検査は食道を含む上部消化管粘膜を直接観察できる検査で、炎症などの病変を発見できます。怪しい病変が見つかった場合、組織を採取して病理検査に回すことで確定診断に繋げられます。また、逆流性食道炎に併発する可能性が高い食道裂孔ヘルニアも調べられます。
近年、食生活の欧米化を背景とし、食道粘膜の一部が胃粘膜に変性するバレット上皮が増加傾向にあります。バレット上皮は食道胃接合部がんの発症リスクが30~100倍上昇するため、定期検診が欠かせません。胃カメラ検査は食道粘膜を直接観察でき、放射線を使うことがなく被ばくリスクもないため、定期的に受けましょう。
当院の胃カメラ検査は内視鏡専門医が担当します。検査による苦痛を最小限に抑えるため、経鼻内視鏡や鎮静剤の使用など、様々な工夫を行っています。胃カメラ検査について分からないことなどあれば、お気軽に当院までご相談ください。
治療
びらんを伴う逆流性食道炎と、びらんを伴わない非びらん性胃食道逆流症(NERD)に分けられます。
治療は胃酸分泌抑制剤などを用いる薬物療法が中心となり、再発を防ぐために生活習慣の改善を行います。症状は簡単に改善できるものの、自己判断で治療を中断すると再発する可能性があるため、医師の指示にしたがって治療を続けましょう。
薬物療法
 薬物療法では胃酸分泌抑制剤が中心となります。
薬物療法では胃酸分泌抑制剤が中心となります。
その他、粘膜保護薬や消化管機能改善薬などを必要に応じて使います。重度の食道裂孔ヘルニアなどの併発が認められる場合、手術を検討します。
治療で使用する主なお薬
-
プロトンポンプ阻害剤(PPI)
胃酸の分泌を抑える効果があり、再発予防に有効です。 -
H2ブロッカー
ヒスタミンH2受容体の働きを阻害し、胃酸の分泌を抑えます。ドラックストアなどでも購入できますが、医療機関では患者様の症状や粘膜の状態に合った適切な容量・服用方法・期間で処方してもらえます。 -
消化管運動機能改善剤
消化管の蠕動運動を促進し、食物の胃内部での滞留時間を短くします。その結果、逆流リスクを低減できます。 -
制酸薬
胃の酸性を弱めて粘膜を保護する作用があり、逆流が発生しても炎症が発生しづらくなります。 -
粘膜保護薬
食道粘膜を保護する作用があり、炎症が起こりづらくなります。
生活習慣の改善
腹部を圧迫するような行動・服装の見直し、胃酸の分泌過多を招く食生活の見直しを行います。逆流性食道炎は再発リスクがあるため、医師に指示にしたがって続けることが重要です。一気に取り組むとストレスの原因となるため、取り組みやすいものから実践していきましょう。
食生活の改善
 高脂肪食や香辛料、酸味のあるもの、甘いものなどは胃酸の分泌を促すため、なるべく控えましょう。また、禁酒・禁煙も症状改善に有効です。便秘になると腹圧が上昇するため、食物繊維と水分をしっかり摂取して便秘を予防しましょう。
高脂肪食や香辛料、酸味のあるもの、甘いものなどは胃酸の分泌を促すため、なるべく控えましょう。また、禁酒・禁煙も症状改善に有効です。便秘になると腹圧が上昇するため、食物繊維と水分をしっかり摂取して便秘を予防しましょう。
姿勢・服装の見直し
猫背や前かがみなどの姿勢は腹圧が上昇し、逆流リスクが高まります。また、ベルトなど腹部を締め付けるような服装は控えましょう。肥満の方はダイエットに取り組むことをお勧めします。
睡眠習慣の見直し
食後すぐに横になると、胃酸など胃の内容物が逆流してしまいます。そのため、食事から2時間以上経過してから横になることを意識しましょう。就寝時に咳やのどに不快感がある場合、背中にクッションなどを敷いて上半身を少し高くすることで逆流症状が起こりづらくなります。
医師の指示にしたがって治療を続けましょう
 問診・検査を通じて原因を特定した上で、原因や炎症の状態、症状などに応じて適切なお薬を処方します。なお、誤ったタイミングで服用すると効果が弱まるため、注意しましょう。
問診・検査を通じて原因を特定した上で、原因や炎症の状態、症状などに応じて適切なお薬を処方します。なお、誤ったタイミングで服用すると効果が弱まるため、注意しましょう。
服用を開始してもすぐに炎症が治まらないこともあります。自己判断で治療を中断した場合、再発リスクがあるため、症状の解消後も医師に指示にしたがって服用を続けることが大切です。
文責:山高クリニック 院長 山高 浩一