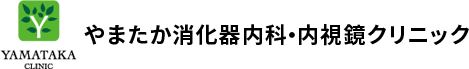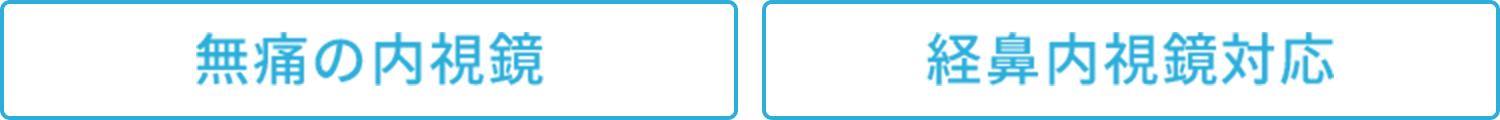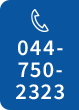ピロリ菌について
 ピロリ菌が経口感染して胃の中で増殖した場合、胃粘膜に慢性的な炎症が発生します。
ピロリ菌が経口感染して胃の中で増殖した場合、胃粘膜に慢性的な炎症が発生します。
この炎症が長期に及ぶと萎縮性胃炎に繋がり、胃がんの発症リスクが高まります。世界保健機構(WHO)の専門組織である「国際がん研究機関」の発表では、世界の胃がんの約8割はピロリ菌が原因とされています。
ピロリ菌は、幼少期に飲んだ井戸水などから感染すると言われており、上下水道が整った先進国では感染率は低下しています。しかし、日本においては感染数が現在も年齢が上がるほど高くなっています。幼少期の生活環境などが影響するため、胃がんの家族歴がある方や、ご家族にピロリ菌陽性の方がいる場合は、ピロリ菌感染検査を受けることをお勧めします。
除菌治療について
ピロリ菌感染検査で陽性と出た場合、除菌治療が必要です。
除菌治療では、抗生物質2種類と、その効果を高める胃酸分泌抑制剤1種類、合計3種類のお薬を1週間服用して頂きます。1次除菌(初回の除菌治療)では成功率が70~80%ほどとなります。1次除菌に失敗した場合、抗生物質を1種類のみ変更して2次除菌に移ります。2次除菌までの成功率は97~98%と言われています。
ピロリ菌除菌の成功は、胃炎や胃潰瘍の再発を防ぎ、胃がんの発症リスクの低減に繋がります。また、ピロリ菌は口移しなどから子どもに感染する可能性もあるため、除菌が成功することで次世代への感染も防げます。ピロリ菌の感染有無を調べる検査、そして陽性反応が出た場合に行う除菌治療は保険が適用されます。胃の不快症状が慢性化している場合、一度当院までご相談ください。
ピロリ菌感染検査について
ピロリ菌感染検査は胃カメラ検査を用いる方法と用いない方法の2つに大別されます。
胃カメラ検査により確定診断を受けることで、除菌治療に保険が適用されます。
胃カメラ検査を用いる方法
 胃カメラ検査により採取した組織を利用し、感染有無を調べます。
胃カメラ検査により採取した組織を利用し、感染有無を調べます。
迅速ウレアーゼ試験
ピロリ菌はウレアーゼという酵素を分泌し、胃の内部に存在する尿素からアンモニアを作り、周囲の胃酸を中和します。迅速ウレアーゼ検査ではこの仕組みを活用し、採取した組織を専用の試薬に加え、pHの値の変化を確認することでピロリ菌の感染有無を間接的に調べます。
胃カメラ検査を用いない方法
尿素呼気試験(UBT)
専用のお薬を飲み、服用前後の呼気からピロリ菌の感染有無を調べます。
感染している場合、ウレアーゼ活性によりお薬に含まれる特殊な尿素が二酸化炭素とアンモニアに分解されます。服用前後でこれらの物質がどの程度増えているか見比べることで、ピロリ菌の感染有無を判断できます。除菌治療の判定検査で使用される場合、検査に保険が適用されます。
抗体測定法
ピロリ菌に感染した場合、体内では抗体が作られます。
抗体測定法は、血液や唾液、尿を採取し、抗体の有無を確認することでピロリ菌の感染を調べます。
便中抗原測定法
便中のピロリ菌の抗原の有無を調べます。
ピロリ菌感染検査に健康保険が適用される条件
 ピロリ菌検査は全て保険が適用されるわけではありません。
ピロリ菌検査は全て保険が適用されるわけではありません。
胃カメラ検査により胃炎や胃・十二指腸潰瘍など特定の疾患が認められた場合と、検査で採取した組織からピロリ菌の感染が認められた場合に限り、保険が適用されます。
6ヶ月以内に人間ドックなどで胃カメラ検査を受けられた方へ
半年以内に実施した胃カメラ検査で、慢性胃炎の診断を受けた方は検査に保険が適用されます。また、ピロリ菌感染検査で陽性反応が出た場合、除菌治療にも保険が適用されます。
ピロリ菌検査・除菌治療が自費診療となるケース
ピロリ菌検査や除菌治療に保険を適用するには、胃カメラ検査が必要となります。
また、2次除菌まで失敗して3次除菌を行う場合は保険が適用されずに自費診療扱いとなります。
保険診療では抗生物質の種類が決められており、サワシリン(ペニシリン系抗生剤)とクラリスロマイシン(クラリス)となっています。これらとは別の抗生剤を使用する場合、保険が適用されません。アレルギーなどによりこれらのお薬が使用できない場合も、自費診療であれば別のお薬を使用できるため、希望される方はお気軽にご相談ください。
除菌治療の流れ
胃カメラ検査により採取した組織からピロリ菌の感染有無を調べます。
陽性反応が出た場合、除菌治療を行います。
11次除菌
除菌治療では、2種類の抗生物質とその効果を高める胃酸分泌抑制剤(PPI)を1週間続けて内服して頂きます。
発生する可能性がある副作用
- 肝機能障害(3%程度)
- 蕁麻疹(5%程度)
- 下痢(13%程度)
- 味覚異常(30%程度)
上記のような副作用が現れた場合、すぐに当院までご相談ください。
特に、咳や喘息、皮膚の腫れ、蕁麻疹、呼吸苦などの副作用が発生した場合、お薬の服用を中止し、速やかに当院をご受診ください。
21次除菌の判定検査
1次除菌から数か月後に判定検査を行えます。当院では、1次除菌終了から1ヶ月後に行っています。
除菌が成功した場合はその時点で治療が終了となりますが、1次除菌の成功率は70~80%となっており、失敗した場合は2次除菌に移ります。
32次除菌
2種類の抗生剤のうち、クラリスをメトロニダゾール(商品名:フラジール)に変更します。
それ以外のお薬は1次除菌と同様です。
42次除菌の判定検査
1回目の判定検査と同じく、除菌治療から1ヶ月後に判定検査を行います。1次除菌・2次除菌を合算した成功率は97~98%となります。
2次除菌も失敗した場合は3次除菌に移ることができますが、保険が適用されず自費診療の扱いとなります。なお、5回目以降の除菌治療で成功したケースもあるため、受けるかどうかお悩みの場合は一度ご相談ください。
文責:山高クリニック 院長 山高 浩一