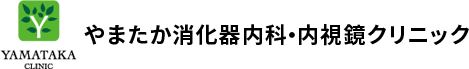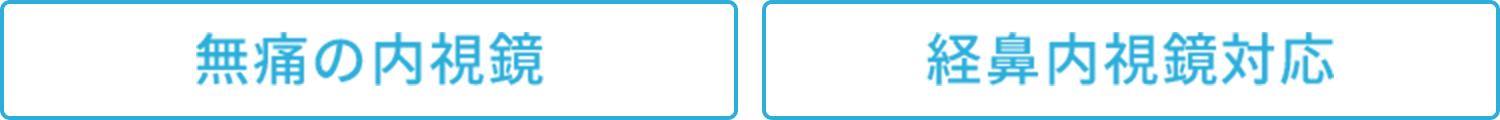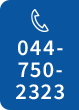生活習慣病とは
 生活習慣病とは、食生活の乱れや運動不足、飲酒、喫煙など生活習慣の乱れによって発症する疾患の総称です。
生活習慣病とは、食生活の乱れや運動不足、飲酒、喫煙など生活習慣の乱れによって発症する疾患の総称です。
主なものには、高血圧症や脂質異常症、糖尿病(2型)、高尿酸血症などが挙げられます。これら疾患の改善・予防のためには生活習慣の改善が欠かせません。なお、生活習慣病を発症して長年治療を受けずに放置していると動脈硬化が進行し、脳梗塞や心筋梗塞などの重篤な疾患に繋がる恐れがあります。
近年は特定健診が一般的になり、リスクを抱えていることが早期に分かるようになりました。健診で異常が見つかった場合、早めに当院までご相談ください。
生活習慣病の主な症状
生活習慣病の代表的な疾患
高血圧
 高血圧は血圧が持続的に高い状態になる疾患です。血圧は、血管内を流れる血液により血管壁にかかる圧力を指します。健康体であれば、最大血圧(収縮期血圧:心臓が収縮し、血液を送り出しているときの圧力)が140mmHg未満となり、最小血圧(拡張期血圧:心臓が拡張し、血液が心臓に戻ってくるときの圧力)が90mmHg未満となります。高血圧は最大血圧あるいは最小血圧が標準値を上回った状態です。
高血圧は血圧が持続的に高い状態になる疾患です。血圧は、血管内を流れる血液により血管壁にかかる圧力を指します。健康体であれば、最大血圧(収縮期血圧:心臓が収縮し、血液を送り出しているときの圧力)が140mmHg未満となり、最小血圧(拡張期血圧:心臓が拡張し、血液が心臓に戻ってくるときの圧力)が90mmHg未満となります。高血圧は最大血圧あるいは最小血圧が標準値を上回った状態です。
高血圧では自覚症状が現れることはほとんどありません。なお、放置していると徐々に血管壁が損傷し、動脈硬化に繋がります。血管は全身のいたるところまで伸びているため、高血圧になると全身に影響が及びます。
特に血管が集中している部位は影響が大きく、例えば、目の網膜や脳、腎臓などは合併症のリスクが高いです。加えて、血液を全身に送り出すポンプの役割を果たす心臓も合併症が起こるリスクがあります。主な合併症には眼底出血や脳梗塞、心不全、腎不全などがあります。こういった深刻な状態を防ぐためにも、健診などで高血圧を指摘された場合、改善に取り組むことが重要です。
高血圧は本態性高血圧と内分泌性高血圧の2種類に分けられます。本態性は原因がはっきりしておらず生活習慣などが関係していると言われており、内分泌性はホルモンの異常な分泌が原因となります。高血圧と診断された場合、原因を特定するためにも精密検査を受けましょう。
脂質異常症
脂質異常症とは血中の脂質が基準値から外れた状態です。血中の脂肪分には、LDL(悪性)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)などが含まれます。
基準値は以下の通りです
- LDL(悪玉)コレステロール:140mg/dL未満
- HDL(善玉)コレステロール:40mg/dL以上
- 中性脂肪:150mg/dL未満
このいずれかが基準値を超えた場合、脂質異常症と診断されます。なお、LDLコレステロールが120〜139mg/dLの範囲にある場合は「境界域」と呼ばれ、高血圧や糖尿病などの発症状況を踏まえて治療の必要性を判断します。
脂質異常症は自覚症状が現れないことが多く、気が付かないうちに動脈硬化が進行します。これにより、脳や心臓などの血流が低下し、脳梗塞や狭心症・心筋梗塞などに繋がり、最悪の場合、命を落とす恐れがあります。そのため、健診などで脂質異常症を指摘された場合、すぐに治療に取り組むことが大切です。
糖尿病
 糖尿病とは血糖値が高い状態が持続する疾患です。
糖尿病とは血糖値が高い状態が持続する疾患です。
膵臓(すい臓)から分泌されるインスリンと呼ばれるホルモンは、食事によって上がった血糖値を下げる働きがあります。糖尿病では、インスリンの分泌量が減少したりインスリンの働きが弱くなり、血糖値が慢性的に高くなります。この状態が長期間に及ぶと、全身の血管が損傷して動脈硬化の進行を招きます。
その結果、様々な合併症を引き起こしますが、特に代表的なものに「網膜症」「神経障害」「腎症」があります。これらを総称して「糖尿病の3大合併症」と呼びます。
1.糖尿病網膜症
目の網膜には毛細血管が隅々まで伸びています。
糖尿病による高血糖状態が持続すると毛細血管が閉塞して網膜に酸素や栄養素が届かなくなり、網膜症を発症します。糖尿病治療を放置、あるいは十分でないと、5年後には10%の確率で網膜症を発症します。時間が長くなるほど発症リスクは高まり、10年後には30%、15年後には50%。20年後には70%となります。網膜症は最悪の場合失明する恐れがあるので、早期発見・早期治療が欠かせません。糖尿病の患者様は定期的に眼科を受診して検査を受けましょう。
2.糖尿病神経障害
糖尿病神経障害とは、自律神経を含む末梢神経が障害される疾患です。
糖尿病神経障害は3大合併症のうち発症リスクが最も高いことで知られており、糖尿病発症から5年ほどで発症する可能性があります。手足の痺れや感覚低下、痛み、発汗異常、立ちくらみ、頑固な便秘や下痢などの症状を示します。重症例では手足の先が壊死し、切断が必要になることがあります。
3.糖尿病腎症
腎臓は血液をろ過し、尿を生成する重要な器官であり、豊富な毛細血管が集まっています。血糖値が長期間(10〜15年)高い状態が続くと、腎臓の濾過機能が次第に衰え、最終的には尿に過剰なタンパク質が含まれるネフローゼ症候群や腎不全を引き起こします。糖尿病による腎症は透析が必要になる最大の原因となっており、その発症数は増加傾向にあります。
痛風(高尿酸血症)
痛風は「風に触れるだけで痛む」と言われるほど激しい痛みが急に発生する関節炎です。
特に、足の親指の付け根付近に起こることが多いです。比較的男性に多く、30~50代に好発します。痛風による激痛は通常、放置していても自然に治まることがほとんどです。そのため、高尿酸血症という痛風発作の原因となる疾患の治療を行わない患者様も多いです。高尿酸血症自体は自覚症状がないため、治療が後回しになることがよくあります。尿酸は細胞の新陳代謝の過程で生じる老廃物で、過剰に蓄積されると高尿酸血症の発症に至ります。この過剰な尿酸が結晶となり、関節や腎臓に沈着し、炎症が起きた状態が痛風発作です。
痛風自体は短期間で解消したとしても、高尿酸血症の治療を行わないと尿酸結晶が残り続けるため、痛風が再発する可能性があります。また、放置すると腎臓病や尿路結石などの合併症を引き起こす可能性もあります。さらに、高尿酸血症の患者様はメタボリックシンドロームを伴っていることが多く、動脈硬化の進行リスクも高いです。
文責:山高クリニック 院長 山高 浩一