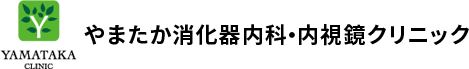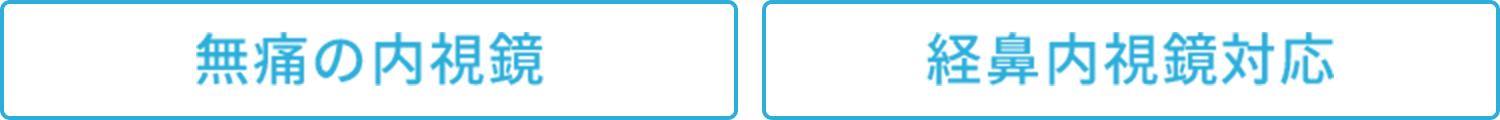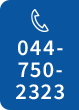過敏性腸症候群(IBS)とは
 過敏性腸症候群とは、腹痛に伴って膨満感、便秘・下痢などの便通異常が続くにもかかわらず、検査において炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどの器質的異常が見つからない状態です。
過敏性腸症候群とは、腹痛に伴って膨満感、便秘・下痢などの便通異常が続くにもかかわらず、検査において炎症や潰瘍、ポリープ、がんなどの器質的異常が見つからない状態です。
検査で異常が発見されない場合も、「体質によるもの」と自己判断して放置するのは控えましょう。過敏性腸症候群による症状は消化器内科にて適切な治療を受けることで、改善が期待できます。
過敏性腸症候群を発症すると、通学・通勤中に急に便意を催したり、症状を繰り返したりすることで、外出が億劫になり、生活の質の大幅な低下を招きます。気になる症状があれば、早めに当院までご相談ください。
過敏性腸症候群の症状・タイプ
過敏性腸症候群の主な症状には、腹痛や膨満感、便通異常が挙げられます。
これらの症状に応じて、「便秘型」、「下痢型」、便秘と下痢を交互に繰り返す「交代型」、膨満感などの症状が強く現れる「その他」に分けられます。
下痢型
下痢型では、突然腹痛が起こり、その後に強い便意を感じて排便すると下痢が排泄されます。症状は緊張する場面で出ることが多く、例えば、会議や商談、試験、満員電車やバスなどが挙げられます。そのため、通勤・通学、職場や学校生活に支障が出る恐れがあります。
便秘型
便秘型は腸が痙攣することにより起こることが多く、激しい腹痛に伴って便秘が起こります。強くいきんでも便は少量しか出ず、コロコロしたウサギのような便が出ます。また、痔などの肛門疾患や大腸疾患に繋がる可能性があります。
交代型
腹痛に伴って便秘と下痢を繰り返します。
過敏性腸症候群の原因
過敏性腸症候群の原因ははっきりとしていませんが、消化管の蠕動運動の異常、消化管の知覚過敏などが影響していると考えられています。
また、消化管の機能は自律神経によってコントロールされているため、ストレスなどの精神的問題により、症状が現れるとも言われています。 感染性腸炎を発症後に過敏性腸症候群を発症することもあるため、炎症により、腸内細菌に変化が生じることを原因とする説もあります。
過敏性腸症候群の診断
腹痛や膨満感、便秘、下痢などの過敏性腸症候群の症状は、他の消化器疾患でも起こるものです。
そのため、血液検査や内視鏡検査により炎症などの器質的異常の確認が必要です。 これらの検査を行って器質的異常が発見されない場合、過敏性腸症候群の疑いがあります。まずは問診により症状などを詳しくお伺いし、その上で国際基準であるRome基準と照らし合わせて診断を下します。
RomeⅣ(R4)
半年以上前から過敏性腸症候群の症状が現れており、直近3ヶ月のうち少なくとも週1回以上症状があり、以下の内容の2つ以上に当てはまる場合、過敏性腸症候群の診断となります。
- 症状の有無に応じて排便頻度が変化する
- 症状の有無に応じて便の形状が変化する
- 排便後に腹痛などの症状が治まる
なお、他の消化器疾患でも同様の症状が現れるため、鑑別診断として大腸カメラ検査や血液検査、便検査、尿検査などを行います。
また、診断基準に一部当てはまらない場合も、症状などから医師の判断により過敏性腸症候群の診断を下すこともあります。そのため、気になる症状があれば、一度当院までご相談ください。早期に治療に取り組むことで症状の改善が期待できます。
過敏性腸症候群の治療
過敏性腸症候群は、命を落とすほど重篤な疾患ではないものの、生活の質の大幅な低下を招く恐れがあります。
完治させるのが困難であり、治療は長期間に及びますが、発症原因・症状について正しく把握できると、発症前と変わらない生活を送れます。 過敏性腸症候群の治療では、症状・体調に応じた薬物療法と、食生活を含む生活習慣の改善や運動療法を行います。
生活習慣の改善
食生活の乱れや睡眠不足は症状の悪化を招くため、生活習慣の見直しが大切です。
自己判断で治療を中断すると症状が再発するため、医師の指示にしたがって継続する必要があります。身体に対する食事の影響は個人差があるため、ご自身に適した改善方法を把握することが大切です。無理のないものから取り組みましょう。
運動療法
 運動により血流を促すことで腸機能を正常化させられます。
運動により血流を促すことで腸機能を正常化させられます。
ハードなトレーニングは必要なく、日頃から取り組みやすい軽い有酸素運動が有効です。医師と相談の上、ご自身に適した運動を取り組んでみましょう。
薬物療法
 症状改善のために薬物療法を行います。
症状改善のために薬物療法を行います。
お薬の種類は多岐にわたり、他のお薬と違う作用機序の新薬も登場しているため、症状に応じて複数のお薬を組み合わせて治療します。 同じお薬でも効き目には個人差があるため、定期的に状況をお聞きして処方内容を適宜見直します。不明点などあれば、些細なことでもお気軽にご相談ください。
文責:山高クリニック 院長 山高 浩一