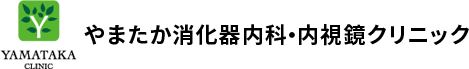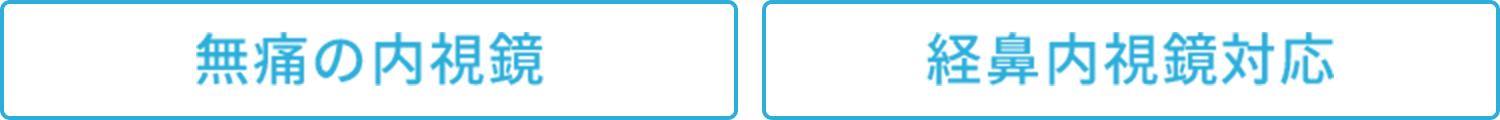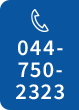- 血便とは
- 下血とは
- 以下のような症状が起きていませんか?
- 血便を引き起こす主な疾患
- 下血を引き起こす主な疾患
- 便の色から判断する健康状態
- 血便・下血に対して行う検査
- 血便や下血が出た場合は当院までご相談ください
血便とは
 便に赤い血液が混ざった状態を血便と言います。
便に赤い血液が混ざった状態を血便と言います。
血便に混ざった赤い血液は、大腸や肛門などの下部消化管からの出血です。出血部位によって血液の色は異なり、大腸では暗赤色となり、肛門では鮮やかな赤色となります。
血便に伴って、痛みや残便感、便秘、下痢、発熱などの症状も現れる場合、深刻な疾患が原因となっていることが考えられるため、すぐに当院までご相談ください。
便潜血とは
血便は目視で便中に混ざった血液が確認できます。しかし、目視では確認できないほど微量の血液が混ざっていることもあり、これを便潜血と言います。便潜血の有無を確認するには便潜血検査が必要です。
下血とは
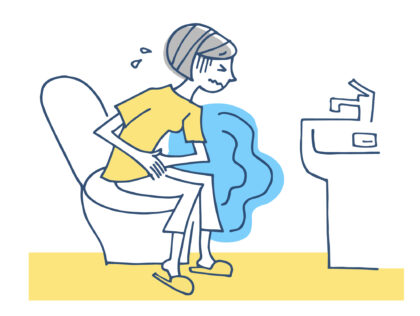 胃・十二指腸などの上部消化管からの出血を下血と言います。
胃・十二指腸などの上部消化管からの出血を下血と言います。
胃・十二指腸からの出血は便に混ざるまでに胃酸や消化酵素によって酸化され、黒っぽい色となります。そのため。コールタールのような色の便(タール便)が排泄されます。大量出血となった場合、暗赤色の便となることもあります。
以下のような症状が起きていませんか?
- 血液が混ざった便が出る
- トイレットペーパーに血液が付着する
- 粘液が混ざった便が出る
- 細い便が出る
- 排便後に残便感を覚える
- 便秘・下痢が繰り返し起こる
- 腹痛が起こる
- 腹部が張っている感覚がある
- 体重が減る
など
血便を引き起こす主な疾患
血便の原因疾患は多岐にわたります。
以下は血便の主な原因疾患ですが、疾患により血便の症状に違いがあります。
痔
血便の原因となる痔は、いぼ痔(痔核)や切れ痔(裂肛)が挙げられます。便表面やトイレットペーパーに血液が付着し、排便後に雫のようにポタポタ滴るような状態が確認されます。 いぼ痔は慢性的な便秘・下痢などにより肛門に負荷がかかり、静脈叢がうっ血して腫れることで発生します。一方、切れ痔は硬い便が通過する際などに肛門が損傷することで発生します。
大腸ポリープ
大腸ポリープは大腸粘膜に発生する良性の腫瘍です。初期では自覚症状が乏しいですが、大きくなると便が通過する際に擦れて出血が発生し、血便が排泄されます。その他、粘液便や便の通過障害、膨満感、腹痛、下痢などの症状が現れます。これらの症状は大腸がんでも起こるため、お悩みの症状があれば早めに当院までご相談ください。
大腸がん
大腸がんの初期では自覚症状が乏しいですが、悪化すると血便や粘液便、腹痛、膨満感、便秘、下痢、残便感、貧血、体重減少、倦怠感などの症状が起こります。 痔が原因となる血便は血液が便表面に付着する程度ですが、大腸がんが原因となる血便では血液が便全体に混ざっていることが確認されます。また、大腸がんと痔を合併していることもあるため、気になる症状があれば検査を受けて大腸がんの早期発見に努めましょう。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は大腸粘膜に発生した慢性的な炎症により、潰瘍が形成される疾患です。原因は明確には分かっていませんが、自己免疫が関わっていると言われており、発症のピークは、20代の若年層です。完治させる治療法が確立されていないことから、厚生労働省より難病指定を受けています。 血液が混ざった下痢便、赤黒い粘血便が排泄されます。下痢症状では激しい腹痛を伴います。その他、倦怠感や食欲不振、体重減少、発熱などの症状も起こります。
虚血性大腸炎
虚血性腸炎とは、大腸に酸素・栄養を運ぶ血流が悪化し、大腸粘膜が虚血状態となり炎症が発生し潰瘍が形成される疾患です。大腸の左側に位置する下行結腸やS状結腸に発生しやすく、左側の下腹部に痛みが現れます。最初に強い腹痛が起こり、その後に下痢や血便が起こります。血便は鮮やかな赤色の血液が混ざり、鮮血のみが出ることもあります。 潰瘍性大腸炎と似た症状を示すため、早めに受診して鑑別診断を受けることが重要です。
細菌性腸炎
細菌が感染することで腸に炎症が発生した状態です。主な原因菌には、カンピロバクターやサルモネラ、病原性大腸菌、腸炎ビブリオなどが挙げられます。各細菌の感染源は、カンピロバクターは鶏肉、サルモネラは卵、病原性大腸菌は牛肉、腸炎ビブリオは魚介類となります。感染性腸炎はウイルス性のものもありますが、血便が出るのは細菌性のものです。 症状は血便に加え、腹痛や下痢、嘔吐、発熱などが挙げられます。
大腸憩室出血
大腸憩室とは、腹圧が上昇して大腸壁の一部が外側に袋を作るように飛び出した状態です。主な原因には便秘が挙げられますが、その他にも加齢に伴い腸壁が薄くなることによって起こることもあり、60代以上で好発します。大腸憩室が形成された場合、炎症(大腸憩室炎)や出血(大腸憩室出血)などが発生することもあり、大腸憩室出血では血便が起こります。また、血便の他にも大量出血が起こることもあります。
クローン病
クローン病は口から肛門に至る消化管全域で慢性的な炎症が発生し、びらんや潰瘍が形成される疾患です。10~20代など若年層に好発する傾向があります。主な症状には腹痛や下痢、粘血便などが挙げられます。その他、体重減少や発熱、痔ろうなどが起こることもあります。こうした症状が起こる活動期(再燃期)と症状が治まる寛解期を繰り返します。
下血を引き起こす主な疾患
胃潰瘍
胃潰瘍とは胃粘膜に潰瘍が形成された状態です。
主な原因には、ピロリ菌感染や過度なストレス、ステロイドや非ステロイド性消炎鎮痛剤などの副作用が挙げられます。また、胃酸や消化酵素による胃粘膜の消化によって潰瘍が形成されることもあります。 胃潰瘍では心窩部痛や背部痛、タール便、吐血などの症状が起こります。痛みは食事中や食後に現れる傾向があります。
十二指腸潰瘍
十二指腸潰瘍は十二指腸粘膜に潰瘍が形成された状態です。ピロリ菌感染によって起こることが多く、20~30代に好発します。十二指腸壁は胃壁に比べて薄いため、出血・穿孔の発生リスクが高いです。十二指腸潰瘍では心窩部痛やタール便、吐血などの症状が起こり、痛みは空腹時や夜間に現れる傾向があります。
体調や健康状態は便の色から判断できます
便は体調や健康状態を把握する指標の1つです。
通常では黄褐色のバナナ状あるいは半練り状の便が快適に排泄されます。崩れやすい、硬い、下痢、通常とは違う色の便が続く場合、消化管で何らかの異常が発生している可能性があります。 以下では、便の色から原因として考えられる疾患について説明します。
便の色から疑われる疾患
便は毎回同じ色になるわけではなく、食事や健康状態、疾患などによって様々な色を示します。
便の色を確認することで、原因をおおよそ把握することが可能です。
黄褐色
通常の便は黄褐色となります。分かりやすく言うと黄土色~薄茶色となります。なお、色は黄褐色であったとしても、繰り返し便秘や下痢が起こる、細い便が出る、血液が便に付着している場合は何らかの異常が疑われるため、一度当院までご相談ください。
黄色
激しい下痢が起きている場合、黄色の便が排泄されることがあります。主な原因には牛乳などの乳製品の過剰摂取、下剤の服用などが挙げられます。なお、下痢が持続する場合、胃腸での感染・疾患の可能性もあります。
茶色~茶褐色
茶色~茶褐色の便は暴飲暴食によって起こることがほとんどです。食事を普段の量に調整し、アルコールを控えることで、ある程度早めに改善が期待できます。
濃褐色
肉類の過剰摂取によって濃褐色の便が排泄されることがあります。また、ココアやチョコレートの過剰摂取も原因の1つに挙げられます。なお、便秘により便中の水分量が減少し、濃褐色の便となることもあるため、食生活を改善しても元に戻らない場合は当院までご相談ください。
黒色
黒色便(タール便)は上部消化管(食道・胃・十二指腸)からの出血が考えられるため、早めに当院までご相談ください。また、ビスマス錠や鉄剤、イカ墨などを摂取して黒色便が出ることもあり、その場合はそれらの摂取を控えることで1日~数日以内に元に戻ります。
緑色
クロロフィルが含まれる緑黄色野菜を過剰摂取した場合、緑色の便が排泄されることがあります。また、消化不良や急性腸炎が原因となることもあります。その他、母乳を飲んでいる乳幼児に見られることもあります。
赤色
大腸がんなどの大腸疾患や痔が原因として考えられます。悪化を防ぐためにも早めに当院までご相談ください。肛門付近からの出血の場合、鮮やかな赤色となります。
灰白色
バリウムを服用後は灰白色の便が出ます。なお、腸結核や肝障害、膵臓疾患、黄疸などによって灰白色の便が出ることもあります。
特に注意が必要な便の色
 以下の3つの便の色が確認された場合、何らかの疾患が疑われるため注意が必要です。
以下の3つの便の色が確認された場合、何らかの疾患が疑われるため注意が必要です。
一度でも以下の色の便が確認された場合、すぐに当院までご相談ください。
黒色の便(タール便)
黒色便(タール便)は上部消化管からの出血が原因となります。出血してすぐは真っ赤ですが、体内を流れるにつれて胃酸などにより酸化され、黒色の血液となります。主な原因疾患には、逆流性食道炎や食道がん、胃潰瘍、胃がん、十二指腸潰瘍、十二指腸がんなどがあります。
赤色の便(鮮血便)
赤い便は肛門や大腸からの出血が原因となります。出血してから間もなく便とともに排泄されるため、鮮やかな赤色となります。主な原因疾患には、いぼ痔や切れ痔、潰瘍性大腸炎、クローン病、虚血性大腸炎、大腸憩室炎、大腸がんなどがあります。
白色の便(白色~レモン色の便)
健康的な便が黄褐色となるのは胆汁に含まれるビリルビンの影響です。白色~レモン色の便は、肝臓や胆管に異常が起こり、胆汁の分泌に支障をきたしていることが考えられます。主な原因疾患には、肝炎や肝不全、総胆管結石、胆管がん、膵臓がん(すい臓がん)などがあります。その他、ロタウイルスの感染が原因となる胃腸炎の可能性もあります。
血便・下血に対して行う検査
血便・下血に対しては以下のような検査を行います。まずは問診にて血便の状態や付随症状、お悩みなどを詳しくお聞きします。
当院では患者様がリラックスして検査を受けて頂けるよう様々な取り組みを行っていますので、安心してご相談ください。
触診と肛門鏡による診察
原因として痔が疑われる場合、肛内指診と肛門鏡による診察を実施します。
肛内指診では、横になって頂きます。手袋にゼリー状の麻酔薬を塗って行うため、痛みはほぼ感じません。肛内指診後に肛門鏡による診察を行います。
胃カメラ検査
 原因として胃・十二指腸など上部消化管の疾患が疑われる場合、胃カメラ検査が有効です。
原因として胃・十二指腸など上部消化管の疾患が疑われる場合、胃カメラ検査が有効です。
胃カメラ検査は、内視鏡スコープを口から挿入する経口内視鏡検査と鼻から挿入する経鼻内視鏡検査がありますが、当院ではいずれにするか患者様に選んで頂いています。どちらの場合でも、苦痛や痛みが軽減されるよう工夫して検査を行います。
大腸カメラ検査
 原因として大腸疾患が疑われる場合、大腸カメラ検査が有効です。
原因として大腸疾患が疑われる場合、大腸カメラ検査が有効です。
当院では、検査に鎮静剤を使用しており、眠ったような状態で検査を受けられるため苦痛を最小限に抑えられます。大腸カメラ検査は大腸全域を直接観察でき、初期の小さながんも見つけられます。大腸ポリープが見つかった場合は、検査中に切除する日帰り手術も行っています。気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
血便や下血が出た場合は当院までご相談ください
 血便や下血はストレスなどによる一時的なものの場合もありますが、がんなどの深刻な疾患によって現れる場合もあります。
血便や下血はストレスなどによる一時的なものの場合もありますが、がんなどの深刻な疾患によって現れる場合もあります。
そのため、胃カメラ検査や大腸カメラ検査などにより原因を特定する必要があります。疾患が原因となっていた場合、その原因疾患に応じて適切な治療を行います。
当院で行う検査・治療は消化器内科の専門医が担当します。患者様のプライバシーに最大限は配慮し、安心して受診して頂けるよう環境を整備しています。また、丁寧な説明も心がけていますので、血便・下血が出た方は一度当院までご相談ください。
文責:山高クリニック 院長 山高 浩一