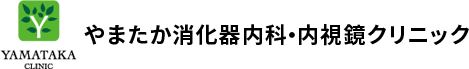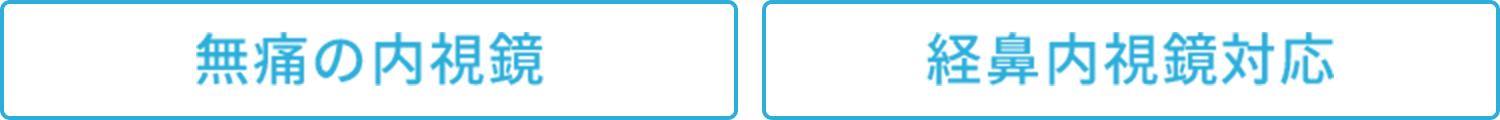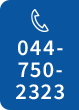便秘について
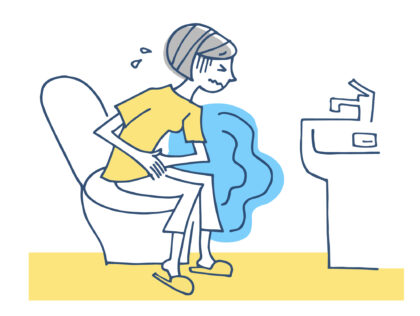 便秘は排便に支障をきたす症状ですが、その状態は多岐にわたります。例えば、細い便が出る、排便後も残便感を覚える、下剤を服用しないと排便できないなどの状態も便秘に該当します。
便秘は排便に支障をきたす症状ですが、その状態は多岐にわたります。例えば、細い便が出る、排便後も残便感を覚える、下剤を服用しないと排便できないなどの状態も便秘に該当します。
排便回数は人によって異なるため、毎日排便できていない=便秘とは言えません。
なお、以下の症状がある場合は早めに医師に相談することをおすすめします。
- 日常生活に支障をきたすほど便秘症状が続く場合
- 便秘に伴って腹痛や膨満感、血便、体重減少などの症状が起きている場合
- 急に便秘になった場合
- 1ヶ月以上にわたり排便が快適にできない状態が続く場合
便秘に伴って高熱(38度以上)が出る場合
通常の便秘では起こりませんが、腸閉塞や他の重篤な状態が原因で便秘になっている場合、発熱が起きる可能性があります。
便秘と熱を併発している場合は早めにご相談ください。
便秘の原因
便秘とは、排便機能異常が発生することで便が腸内に長く留まる状態です。
便秘は、胃・腸・肛門の疾患による「器質性便秘」、大腸機能の低下による「機能性便秘」に大別され、機能性便秘は以下のように細分化されます。
それぞれ発生機序には違いがあります。
直腸性便秘(または便排泄障害型便秘)
直腸性便秘は排便リズムが乱れることにより、直腸の感度が低下し、直腸に便が溜まっても便意を催さなくなることで起こります。
トイレに行く時間がないなど長時間便意を我慢することが原因で発生します。
弛緩性便秘(または通過時間遅延型便秘)
大腸の蠕動運動が弱まることで、便の通過に支障をきたし、大腸内で便が長時間滞留することで起こります。
主な原因には運動不足や食物繊維の摂取不足が挙げられます。様々ある便秘の種類のうち、弛緩性便秘が最もよく認められます。
痙攣性便秘(または通過時間正常型便秘)
大腸の蠕動運動は自律神経によって制御されています。
痙攣性便秘は自律神経が乱れることで大腸の蠕動運動が亢進し、腸管が痙攣して起こる便秘です。腸の痙攣は大腸への過度なストレスや緊張などによって起こります。このタイプでは、便秘に加えて腹痛や膨満感などの症状も示します。
―他にも、薬剤性の便秘や神経・ホルモンの疾患による便秘もあります。
便秘を引き起こす主な疾患
以下が便秘の原因となる主な疾患です。
大腸がん
大腸がんは近年発症数が増加傾向にあります。これは食生活の欧米化が背景にあると言われています。
特に、動物性脂肪は消化のために多くの胆汁酸が必要となり、胆汁酸が腸内に長時間残ると発がん性物質に変化するため、大腸がんの発症リスクが高まります。また、食物繊維の摂取不足も要因となります。大腸がんは初期では自覚症状が乏しいため、早期発見のためにも定期的に大腸カメラ検査を受けましょう。
過敏性腸症候群(IBS)
過敏性腸症候群は、消化管に器質的異常がないのにもかかわらず、腹痛に伴って便秘や下痢などの便通異常が繰り返し起こる疾患です。
過敏性腸症候群で起こる便秘は痙攣性便秘に当たります。心身のストレスにより再発リスクがあるため、ストレスを溜め込まないように気を付けましょう。
腸閉塞(イレウス)
腸閉塞(イレウス)とは、腸捻転や腫瘍、腸機能障害により腸管が閉塞し、便の通過に支障をきたす状態です。
腸内に便やガスが滞留し、腹痛や膨満感、嘔吐、発熱などの症状が現れます。
便秘の検査
 まずは問診にて便秘の状態や付随症状の有無、生活習慣、既往歴、飲まれているお薬などについて詳しくお聞きします。その後、必要に応じて腹部の触診や血液検査、腹部超音波検査、腹部レントゲン検査、大腸カメラ検査などを実施します。何らかの疾患が疑われる場合、血液検査を実施します。
まずは問診にて便秘の状態や付随症状の有無、生活習慣、既往歴、飲まれているお薬などについて詳しくお聞きします。その後、必要に応じて腹部の触診や血液検査、腹部超音波検査、腹部レントゲン検査、大腸カメラ検査などを実施します。何らかの疾患が疑われる場合、血液検査を実施します。
また、器質的異常が疑われる場合は大腸カメラ検査を実施します。大腸カメラ検査は大腸全域をリアルタイムで観察可能で、疑わしい病原を見つけた場合は組織を採取して病理検査に回すことで、確定診断に繋げられます。
当院では、最新鋭の内視鏡システムを導入しており、非常に小さな病変でもスムーズに見つけられます。
便秘の治療
食事療法
食事は栄養バランスの整ったメニューをなるべく決まった時間に摂りましょう。
また、食物繊維や水分をしっかり摂ることも意識してください。 ダイエットに取り組んでいる場合、食事量を減らすことで便秘が発生しやすくなります。当院では、摂取カロリーの調整も適切なアドバイスを行っています。
運動療法
有酸素運動が便秘の解消に有効です。ハードなトレーニングではなく、散歩や階段の昇降など日頃から行いやすい軽いもので大丈夫です。
適度な運動を習慣化することで、筋力が付いて基礎代謝が高まります。その結果、血行が良くなることで腸機能の改善が期待できます。ストレッチなどもお勧めです。
生活習慣改善
栄養バランスの整った食事や睡眠時間を十分に確保することで、腸機能の改善が期待できます。
また、便意を催した場合はすぐにトイレに行くことが重要です。こうした生活習慣の改善は、便秘だけでなく全身の健康状態にも良い影響をもたらします。また、入浴も全身の体温が高まり、血流が良くなるため便秘改善に寄与します。ストレスは便秘の発生・悪化に関係するため、ストレスを溜め込まないようにリフレッシュできる時間を設けましょう。
薬物療法
市販薬でも便秘の解消が見込めますが、使い続けると徐々に効果が弱まります。
また、かえって便秘が悪化することもあります。そのため、医療機関を受診して便秘の状態・原因に応じた適切なお薬を処方してもらう方がより高い効果が期待できます。当院では患者様の状態に応じたきめ細かな処方を行えます。分からないことなどがあれば、お気軽にご相談ください。
文責:山高クリニック 院長 山高 浩一